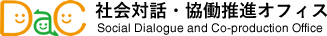【連載】ミヤザキが行く!研究者に“突撃”インタビュー
-教えて辻さん!地域社会への関心から災害復興研究を始めたのはなぜ?社会学の視点と共に伺います
連載「ミヤザキが行く!研究者に“突撃”インタビュー」。インタビュアーは“ミヤザキ”こと、宮﨑紗矢香です。
環境研究の研究者ってどんな人?どんな社会を望んで研究しているの?背景にある思いなどをミヤザキ目線で深堀りし、研究、人柄の両面から紹介します!
Vol.12:辻岳史さん(災害復興の専門家)

第12回のゲスト研究者、辻さん(右)と筆者。
2011年に発生した東日本大震災および福島第一原子力発電所事故は、周辺地域の人々の暮らしに甚大な影響を与えました。放射性物質による汚染や、住民の広域避難と帰還の遅れ、地域コミュニティ活動の停滞など、 さまざまな困難に直面する中で、復興という長い道のりをどのように形づくっていくのか、多くの人が苦悩を重ねてきました。
今回は、津波や原発事故の被災地域でのフィールドワークを通じて、地域で活動する集団や組織が、どのように関わりながら災害復興を進めるのかを記録・分析している辻さんにお話を伺います。多様な人々と対話を重ねる辻さんの歩みとは?
連載のバックナンバーはこちら
Vol.01:江守正多さん(地球温暖化の専門家)
インタビュアー:宮﨑紗矢香
対話オフィス所属、コミュニケーター。大学時代、環境活動家グレタ・トゥーンベリさんのスピーチに心を動かされ、気候変動対策を求めるムーブメント、Fridays For Future(未来のための金曜日/以下、FFF)で活動。
出版社の営業から一転、大学院へ。背中を押したのは、兄の言葉と生まれ育った地域への思い
宮﨑 本日はよろしくお願いします。まずは辻さんが研究者になった経緯について聞かせてください。
辻 同志社大学の文学部社会学科を卒業し、通信教育等を行う会社で出版事業の営業として、学校を訪問し参考書を販売するという仕事をしていました。転勤が多く、赴任先の大阪や福岡、名古屋など全国の学校を転々とする中で、以前から地域社会や都市、町の成り立ちに興味があったこともあり、もう少し勉強したいなという気持ちになって、勢いで会社を辞めて大学院に入ることにしました。今思えば無茶だったなと思いますが(笑)
もともと趣味で都市についての批評をよく読んでいたのですが、当時、兄から「お前は都市批評のような文献研究よりも、人を相手にする社会学の方が向いているぞ」と言われて。地元の名古屋にある名古屋大学大学院環境学研究科の社会学講座(修士課程)に進学し、地域社会学の研究を始めました。ちなみに兄の辻泰岳(東京大学総合研究博物館)も研究者で 、建築史や美術史が専門です。
宮﨑 へえーそうなんですね!地域社会や町に興味があるというのは、何かきっかけがあったのでしょうか?
辻 生まれが名古屋市の名東区という、いわゆる郊外住宅地なんです。1970年代に一気に開発が進んで住宅地ができたような場所で、私が小学生のときは子供たちがたくさんいて、元気な町だったんですね。
でも私が社会人になった頃はかなり高齢化が進んでいて、同世代もよその地域に住むようになり、郊外の縮小や過疎化といった現象が見られるようになってきたんです。かつて自分が生まれ育った地域の元気のない現状を目の当たりにして、この先どうやったら郊外地域は存続していけるのか?という点に関心を持つようになりました。
宮﨑 なるほど。地方に転勤した経験もあってのことなんですかね。
辻 そうですね。地域の多様性というか、同じ県でも自治体が違うだけで雰囲気や成り立ち、主要産業も全く異なるので、営業していたときも面白いなと思っていました。
例えば、生まれ育った名東区は当時地下鉄しか走っていなくて、高校で入っていた野球部で遠征したときにはじめて踏切を見たんです。そうしたささやかなところ一つとっても、自分が生まれ育った郊外と他の地域との違いは、興味深く感じていました。
福島で災害復興の研究を開始。被災地域で利害調整を再構築する難しさにも直面
宮﨑 今は国立環境研究所(以下、国環研)の福島拠点の所属ですが、福島に着任するまでの経緯についても伺いたいです。
辻 名古屋大学大学院の修士課程に入ってから、縮小していく地域の存続や、持続可能性について調査したいと思って調べていたのですが、指導教官の黒田由彦先生(現・椙山女学園大学)から研究のフィールドとして、東日本大震災の津波被災地域を勧められました。たしかに、津波の被害を受けた地域はこれからも町が続いていくかどうかの瀬戸際にあるなと納得し、災害復興の研究を始めました。2012年2月に宮城県東松島市を訪問して、自治体職員や住民団体の方々にインタビュー調査をしたり、復興事業として計画された高台への集団移転について、住民と行政がどのように議論しながら進めていったのかという分析をしたりしました。
その後の博士課程では、災害復興のプロセスにおける地域の多様性について比較研究をしました。復興が早い地域と遅い地域があるけれど、そのスピードの違いは何で説明できるのか?という問いを立て、「コミュニティ・ガバナンス」という、行政や住民の方々が震災前から構築している人間関係などに要因があるのではないかとまとめました(※注1)。
国環研には2017年に入所したのですが、被災地で復興の研究をしたかったというところと、福島県の研究がしたかったという興味関心が合致したんです。福島県は放射性物質の汚染や帰還困難区域の問題、政治的な利害などさまざまな問題が複雑に絡み合っていて、宮城県とは比べものにならないほど復興の道のりも大変だろうなと思い、いつか自分の研究テーマとしてチャレンジしたいと思っていました。
あとは環境的な視点ですね。一般的に日本の復興事業ではスピードが求められるので、災害発生直後の時期は環境への配慮が後回しになりがちですが、福島県は原発事故の教訓をふまえて再生可能エネルギーの導入にも力を入れています。これまで自分がやってきた災害復興の研究に、環境問題という新しい視点を加えて調査研究を進められるのではないかという感触があり、応募しました。
※注1 辻岳史(2023)『コミュニティ・ガバナンスと災害復興:東日本大震災・津波被災地域の復興誌』晃洋書房はこちら
宮﨑 なるほど。これまで復興ガバナンスの研究をされてきたということですが、実際に被災地域で人間関係を構築することや、利害調整を行うことの難しさについてはいかがでしょうか?
辻 国の復興制度・復興政策の方針で、福島県には莫大な予算が投じられ、複雑な復興事業のメニューが整備されています。被災地域はこうした予算や事業をうまく使って復興を進める必要があるのですが、そもそも復興政策を決めていく地域の仕組みが、震災や原発事故前とはかけ離れたものになってしまっています。
もともと地域にいた人々は大半が避難されているほか、震災後の移住政策で新しく住み始めた方もいて、全く違う人が住むようになっているんですね。以前この地域では、他の地域の町内会・自治会・町会にあたる「行政区」という地域住民組織が、住民が政策に参加する窓口になっていたのですが、こうした行政区が従来の機能を果たすことが難しくなっている状況で、復興についての政策や物事を決めたり、利害を調整したりするための仕組みを一から再構築しなければいけないという難しさがありますね。

大熊町住民の方へのインタビュー調査の様子(2025年2月12日)
宮﨑 利害調整などのプロセスは骨の折れる作業だと思うので、研究者として長く関わっているということは、本当にすごいなと思います。
辻 被災地で利害調整を担っているのは主に自治体職員や住民団体の方々などですが、人手やノウハウが限られるなかで、住民のニーズを復興政策に反映していく余裕があまりないのが現状です。そこでわたしたちは、住民の方々の意見や要望を聞き入れながら、復興・環境政策を進めていけるような対話の場づくりやワークショップなどの提案をしています。
「やっかいな問題」における「対話の場」の役割。多様な価値観に気づくきっかけに
宮﨑 辻さんはかねてより、環境問題や災害復興をはじめ、何が問題かがはっきりと定義されておらず、解決方法についても合意がされていない「やっかいな問題」をめぐっては、さまざまな考えをもつ人々が集まる「対話の場」をつくる必要があると指摘されていますが(※注2)、「対話の場」の役割についてはどう考えていますか?
※注2 詳細は、“ふくしまから地域と環境の未来を考えるWEBマガジン” FRECC+(フレックプラス)「地域環境問題はなぜ「もめてしまう」のですか?」を参照
辻 今、まさに対話の場づくり支援で浪江町津島地区に関わっています。津島地区は福島原発事故による高濃度汚染の影響をうけて全域に避難指示が出されたところで、他の地区に比べて除染や住民の帰還、復興事業の遅れが目立つ地域なんです。国と事故を起こした東京電力を被告として住民が起こした集団訴訟の動きもあります。
現地の住民や行政区長さんは「森林や里山を除染して、事故前のように利用できるようにしたい」と望んでいるのですが、環境省としてはコストもかかるし、除染はできないという方針をすでに示していて。そうしたなかでも、森林資源を活用していくためにはどうすればいいか、住民の方と一緒に調査をしながら進めていこうとしています。その過程で、住民が地域に対してどのような思いをもっているかという価値観やニーズを拾い上げていくために、2024年度から地域住民の方々、企業、福島国際研究教育機構(F-REI)や早稲田大学ふくしま浜通り未来創造リサーチセンターの研究者と協力して対話の場を設けています(※注3)。
ここでの経験もふまえて思うことは、対話の場というのは、相手によって設計の仕方も目的も変わってくるということです。何らかの政策決定にむけた利害調整や合意形成のためにおこなう対話もあれば、気候市民会議(※注4)のように、こうした側面だけではなく、参加した人が自分や他者が抱えている利害や価値観に気づくきっかけになる対話もあります。社会学の議論で「再帰性」という言葉がありますが、他者と対話することで自分のあり方を見つめ直すというように、自分が気づいていなかった多様な利害や価値、課題を再認識することが目的の対話があってもいいと思います。
※注3 詳細は、2025年5月16日実施「津島地区における森林との関わりについて考える「対話の場」」を参照
※注4 気候市民会議とは:無作為に抽出された市民が専門家による話題提供を踏まえて、対話と熟慮と投票を繰り返し、気候変動対策をまとめ、提言するもの。
宮﨑 私も社会学部出身なので、他者の存在が自己のあり方に変容を及ぼす対話の重要性を改めて実感しました。ちなみに、国環研の研究者は理系が多いですが、数少ない人文社会系の社会学者として貢献したいと考えていることはありますか?
辻 国環研に入所してからはむしろ、自然科学や工学、社会科学の他分野の研究者に刺激されて、社会学の独自性を意識することが少なくなってきました。分野は違っても目指す目的や方向性は大きく変わらないので。たとえば福島の研究であれば、住民の声を反映しながら、環境に配慮したまちづくりを進めていく、という視点はみな一致しています。
宮﨑 なるほど。一方で、最近は研究所の外部評価などでも、国環研における人文社会系の研究の重要性が指摘される場面も多くみられ、所外や社会からのニーズは高まっていると思いますが、いかがでしょうか?
辻 そうですね。これは社会学だけでなく、環境経済学や政治学にも共通する視点だと思うのですが、社会が多様な価値観をもつ人たちで成り立っていることを前提に、さまざまな視点、立場で政策や意思決定を進めていく必要があると感じています。
社会の中にはたくさん資源を持っている人もいれば、それほど持っていない人もいて、そこにはさまざまな格差があります。そのなかで経済学は所得格差に、政治学は政治的な資源の分配というところで、権力や政治に届く声と届かない声という格差に目を向けますよね。社会学は社会的な関係資源や、属性や立場によっても異なる人々の価値観の格差に目を向けることが多いです。こうした実態を明らかにする役割が人文社会科学にはあると思います。それは、自然科学や工学分野は必ずしも得意ではない部分かもしれません。

宮城県名取市閖上で開催した調査報告会・対話企画の風景(2023年9月15日)
将来世代の声をどのように意思決定に反映させるか。大人も責任を果たす必要がある
宮﨑 昨今の国際情勢や選挙報道を見てもそうですが、国内外でイデオロギーの対立が激しさを増す中で、人文社会系の役割はますます求められていきそうですね。
辻さんは、将来世代を考える研究「Beyond Generation」プロジェクト(以下、BGプロジェクト)にも参加していますが、災害復興の研究を進める中で、どういう観点から将来世代に着目されたのでしょうか?
辻 そもそも大規模な災害から被災地域が復興を遂げるまでには、とても長い時間がかかります。復興に要する時間が世代をまたぐだけではなく、財政的な負担を将来世代が負うことになる可能性もあるため、彼らの声は政策決定に反映される必要があるのですが、復興における議論において将来世代はステークホルダーに位置づけられていない現状があります。そのため、災害復興のような長期的な公共政策を考える上では、制度としてどのように位置付ければ将来世代が考慮されるのかという問題意識があり、BGプロジェクトに参加してきました(※注5)
※注5 辻さんによるBGプロジェクトコラム「世代をまたぐ社会的営みとしての災害復興」はこちら
宮﨑 辻さんの問題意識には共感します。福島拠点でも被災地の高校で探究学習支援に関わっていると聞いていますが、彼らと交流する中で感じてきたことはありますか?
辻 これはどう受け止められるかわからないですが、福島の高校生はとにかく大人からいろいろな期待をかけられているんですよね。福島の復興を担うのは若いあなたたちです、だから頑張ってねとか。気候変動問題もそうですが、これは将来にわたる話だから若い人たちがどうにかしないと変わらないから頑張ってくださいと言われていることが多くて。期待をかけられる方としてはちょっと苦しいのではないかと思います。若者を応援するのは大事なことですが、若い人たちだけに期待をかけて、我々現役世代の責任が問われなかったり、責任が回避されたりすることはよくないと思っています。
宮﨑 私も大学生のときに、気候変動問題に対して声をあげていたことがありますが、同じような活動をしている今の若者と話すと、やはり葛藤を抱えていて。被害を受けるのはこれからの時代を生きる若者だから、自分たちが声を上げていかないといけないという使命感がありつつも、高齢世代から応援されることに疑問を感じたり、メディアからアイコン化されて、責任を背負わされるのは違うのではないかとジレンマを感じているようです。
辻 社会運動の戦略として、若者が訴えることの有効性はあると思いますが、それをすることでかえって若者がアイコン化され、消費されてしまう側面がありますよね。若い人たちが訴えていることなんだから、若い人たちが頑張ってくださいねと、本筋の政治的な意思決定からははじかれてしまうというか。利害調整は相変わらず上の世代がビジネスの論理で決めるみたいな形になってしまうと、やっぱりすごくまずいですよね。若い人たちも含めて、世代を横断するような形で連携できる仕組みが大事だと思いますが、どうやっていけばいいか。難しいですね。
宮﨑 グレタさんのFFF運動も下火になりつつある中で、これからどのように機運を盛り返していくのかは、引き続き私も考えていきたいです。
辻 福島の被災者の方々もそうなのですが、若い人たちも時間が経って、それぞれのライフステージも変わっていくなかで、これまでのような熱意や労力を社会運動にかけることが難しくなる時期もあると思います。だからこそ、若者だけに期待をかけ続けるのではなく、どのようにして他のセクターや世代が支援していけるのか、何かしらの制度や政策が求められてきているのかもしれないと思いました。
宮﨑 そうですよね。私は京都議定書が採択された年に生まれて、地球温暖化とともに歳を重ねているので「京都議定書生まれ、温暖化育ち」を自称していますが、今の若者は、現在進行形で気候変動が進む中で人生を歩んでいるので、これまでにない世代なのではないかと思うことが多いです。改めて、本日はお話ありがとうございました!
<対談を終えて>
社会学という共通のバックグラウンドから、勝手に親近感を感じていたこともあり、話を聞く日を心待ちにしていました。人を相手にする社会学が向いている、とお兄さんが言っていたように、被災地をはじめ日頃から様々な人と接している様子が伺い知れるような、包摂的で丁寧な語り口に、自分もこんな研究者になりたいと思わされました。
環境問題や自然災害からの復興など、「やっかいな問題」が山積している現代ですが、社会は多様な価値観を持つ人で成り立っているという辻さんの言葉に立ち返り、対話することを諦めない姿勢を持ち続けたいと思いました。辻さん、ありがとうございました!
[掲載日:2025年9月16日]
取材協力:国立環境研究所 福島地域協働研究拠点(地域環境創生研究室)辻岳史主任研究員
取材、構成、文:宮﨑紗矢香(対話オフィス)
【連載】ミヤザキが行く!研究者に“突撃”インタビュー
●Vol.02:田崎智宏さん(資源循環・廃棄物管理の専門家)
●Vol.06:番外編①「IPCC」を考察するセミナー報告記事
●Vol.06:番外編②Kari De Pryckさん(科学技術社会論の専門家)
●Vol.09:HARTWIG Manuela Gertrud(ハルトヴィッヒ・マヌエラ・ゲルトルト)さん(社会学の専門家)