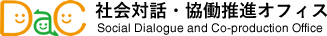【連載】ミヤザキが行く!研究者に“突撃”インタビュー
-教えて久保田さん!環境に興味がない学生時代から環境法の研究を始めたのはなぜ?日本における人権意識と共に伺います
連載「ミヤザキが行く!研究者に“突撃”インタビュー」。インタビュアーは“ミヤザキ”こと、宮﨑紗矢香です。
環境研究の研究者ってどんな人?どんな社会を望んで研究しているの?背景にある思いなどをミヤザキ目線で深堀りし、研究、人柄の両面から紹介します!
Vol.10:久保田泉さん(環境法の専門家)

第10回のゲスト研究者、久保田さん(右)と筆者。
気候変動や海洋汚染、廃棄物の不法投棄など、人類の生存に関わる事態が地球規模で生じる中、世界では、環境問題の深刻化を防ぐための様々な法律や国際条約が制定されてきました。
今回は、環境の保全や改善を図る制度を研究する環境法の専門家、久保田泉さんにお話を伺います。国立環境研究所(以下、国環研)で唯一の法学研究者である久保田さんの、環境にも法律にも関心がなかったという意外な大学生時代とは?根掘り葉掘り、聞いていきます!
連載のバックナンバーはこちら
Vol.01:江守正多さん(地球温暖化の専門家)
インタビュアー:宮﨑紗矢香
対話オフィス所属、コミュニケーター。大学時代、環境活動家グレタ・トゥーンベリさんのスピーチに心を動かされ、気候変動対策を求めるムーブメント、Fridays For Future(未来のための金曜日/以下、FFF)で活動。
不法投棄のドキュメンタリー番組に衝撃を受け、環境法の面白さに目覚めた学生時代
宮﨑 本日はよろしくお願いします。久保田さんが、環境法に関する研究を志すようになった経緯について教えてください。
久保田 子供の頃に、母とスーパーに行ったときの体験が原点になっていると思います。
母は専門家ではありませんが、生協や生活クラブを使っていて、環境に対してそれなりに関心がある人でした。買い物で手に取ったトイレットペーパーが少し高いものだったので、「なんで一番安いものを買わないの?」と聞いたら、「古い紙をもう一回使っているものだから、少し高いけど環境にはいいのよ」と言われて。
その時に、環境によいことをするために余計にお金を払う理由がよくわからないなと思ったんです。個人の根性に頼る環境改善は続かないし、よくないと思う原点でした。
宮﨑 なるほど。環境に熱心なお母さんの行動を支持するのではなく、疑問を持って見ていたんですね。
久保田 はい。それ以降も環境に関してすごく興味があったわけではないのですが、世の中のことを知りたかったので、学習院大学の法学部政治学科に進学しました。
大学3年生のときに「行政法」という授業があり、香川県の豊島(てしま)で問題になっていた不法投棄のドキュメンタリー番組を見ました。人の背丈以上にもなる巨大なゴミの山を築いてしまった産廃処理業者に対して、記者がこんな大量のゴミを捨てるのはなぜかと問うのですが、業者は「これはゴミではなく資源なんです」と答えていました。
誰が見てもゴミにしか思えないのに、これが資源というのはどういうことだろうと衝撃を受けましたが、番組を見た後に先生が「業者の言っていることはおかしいと思ったかもしれないけれど、今の法律では本当に資源になるんだ」と話していて。

豊島を訪れた際に展示されていた廃棄物の模型(2018年)
当時の廃棄物に関する法律では、有価物か無価物か(価値があるかないか)という基準があり、どんな巨大なゴミの山でも一円の価値がつけば有価物と判断されるので、廃棄物を管理する法の対象外とされていたんです。
世の中にそんなことがあるのかと驚くと同時に、法律はルールだから、ルールによって誰が見てもゴミであるものがゴミじゃないとされるなら、逆のことも法律にしかできないことだと思い、ルールをつくる、定めるということは、実は面白くて重要なことなのかもしれないと気付きました。
それから法律に関心をもつようになり、国際法のゼミに入りました。ゼミでは国際法模擬裁判(※注1)に取り組んでいて、大学対抗の大会に出場しました。そこで、被告弁論の部で1位をとることができました。それまで人生で一番をとったことがなかったので、その経験は、自信につながりました。
※注1 国際法模擬裁判とは:架空の国際紛争を題材にするディベートの一種で、原告・被告双方の立場から国際法に基づく論理を組み立て、弁論などを競い合うもの。
宮﨑 香川県豊島の問題は知らなかったので、ぜひドキュメンタリーを見てみたいです。学生の頃は、環境のことも法律にも関心がなかったというエピソードに驚きました。
久保田 当時は新聞記者になりたいと思っていたのですが、自分は就職活動をすることに向いていないと痛感し(笑)、あと2年勉強するのもありなのではないかと思い、大学院に進みました。そのくらい行政法や環境法の勉強が面白かったし、世の中とつながっていると感じました。
博士課程進学後は三菱総研でインターンを経験し、大学以外の世界も見てみたのですが、当時、国環研の研究者だった亀山康子さん(※注2)が温暖化の国際交渉について研究をする研究員を募集していて、運よく採用してもらうことができました。ただ、温暖化は法政策で解決できる問題ではなさそうという理由で、環境問題の中でもあまり興味がありませんでした。
大学4年生のときに京都でCOP3(第3回気候変動枠組条約締約国会議)が開催され、当時の指導教授から「こんなに大きな国際会議を日本で見られることは滅多にない。国際環境法を専攻するなら見ておいた方が良い」と傍聴を勧められたのですが、温暖化には興味ないので、の一言でバッサリと断ってしまったほどです(笑)当時は気候変動の国際交渉というものが政治の力で動いているイメージがあり、温暖化の影響の重要性を理解できず、環境問題の解決には携わりたいけど温暖化にはどうやって貢献できるのかなと思っていました。
そのため、国環研に入所してからは苦労しました。温暖化について一から勉強する必要があった上に、理学工学分野の研究者が大半の世界に法学の世界から入ったためギャップも大きかったです。研究スタイルも、一人で論文を執筆するよりチームで書くということにも戸惑いを感じ、いまだに戸惑っています。
宮﨑 以前インタビューをした福島拠点の中村さん(※注3)も、研究所に入ってからは異分野の人とのやりとりが新鮮だったという話をしていました。
※注2・注3 亀山さん、中村さんへの突撃インタビュー記事はこちら
久保田 もともと理数系科目は苦手でした。たとえば、気候モデルの研究者が何をしようとしているのか理解できなかったのですが、所内でひたすら聞いているうちに、大まかにですが、少しずつわかるようになりました。次第に、専門の法学研究と自然科学分野の研究とをつなぐことができたらと思うようにもなりました。大学やシンクタンクにはない研究所の環境は、得られることも多かったです。
宮﨑 大学院を卒業してから現在に至るまで、ずっと国環研にいるのはすごいです。
久保田 在外研究で一年間アメリカに行きましたが、それ以外はずっと国環研です。入所した頃は雇用状態が不安定で、その頃はまだつくばエクスプレスも通っていなかったのですが、つくばエクスプレスが開業するまで研究所にいられるのか心もとない状況でした(笑)。
自分には関係ないと線を引いてしまう日本人の傾向ー気候変動と人権問題をめぐって
宮﨑 久保田さんはIPCC(気候変動に関する政府間パネル)第6次評価報告書の主執筆者でもありますが、執筆に関する経験談を聞かせてください。
久保田 日本で法学を専門としながらIPCCの報告者の主執筆者を経験した人は、過去に一人いらして、あとは私だけです。国環研は比較的、執筆者や執筆経験者が多い環境だったので、周囲に助けられながら書くことができました。
IPCCの執筆者は、世界中で発表された学術論文を集約し評価することで原稿を作成します。執筆に参加していない世界中の研究者や各国の政府も、作成された原稿に対して自由にコメントすることができるのですが、執筆者はその何万ものコメントすべてに対応する必要があります。実際、ちょっとずれているのではないのかなというコメントも届くのですが、その全てを確認して、これは受け入れる、受け入れないを判断し、その理由まで書くのはなかなか大変な作業でした。
連携という意味では研究所に入った当初、環境省の交渉担当者の補佐役としてCOP(国連気候変動枠組条約締約国会議)の日本政府代表団に入れてもらい、国際交渉のお手伝いをしていたのですが、日本人は議論をして一つのものを作り上げていく作業に慣れていないということを痛感しました。
教育の問題もありますが、いわゆる「根回し」みたいなことがよくある社会というのも関係しているのかなと思います。私は国際交渉の現場に身を置いたことで、幅広い分野の研究者やいろんな国の方とチームで仕事ができ、職業人生の中でも得難い経験をすることができました。

COP20会場ゲート前にて(2014年12月)
宮﨑 久保田さんが取材を受けていた研究所の記事(※注4)に、「COPから帰国して日本の報道に接すると、長期的に温室効果ガスを減らすことが重要なのに、どうしても日々の報道は目先のことばかりで、そのギャップからまるで違う会議に出ていたような気持ちにもなった」というコメントがありましたが、日本の環境対策は長期的な視点での議論よりも、どちらかというと日々の暮らしに則した、まさに個人の根性に任せがちな話が多いと思います。研究者として国際会議の動向を追う中で、このあたりが改善されている感触はありますか?
※注4 「地球環境研究センターニュース」(2015年6月号)の記事はこちら
久保田 気候変動対策の話になると、「個人にできることは何ですか」と聞かれることは依然として多いです。IPCCの第6次評価報告書のレポートにも、社会を変革していく必要があるというメッセージが打ち出されていますが、なかなか伝わりません。
日本では、“現場の声”をとても重んじる傾向があると感じています。現場経験があることは悪いことではないですが、ボトムアップもトップダウンも両方必要な中で、現場の積み上げにこだわることは重要なのかなと疑問に感じます。
また、必要なのは社会を変えることだと言うと、自分には関係ないとシャッターをおろされてしまうところがありますよね。廃棄物などは興味を持たれやすいテーマですが、温暖化のように話の抽象度があがり、時間軸が長いものになると難しくなってしまうようで、わかりやすく伝えることは重要ですが、世の中にはわかりやすい問題ばかりではないのにと思うことはあります。
宮﨑 日本は現場を重んじる傾向が強いというのは、私も感じています。地道にコツコツと、現場経験を積んでからでないと発言できないみたいな、職人的な世界観があるというか。人生経験としては大事なことですが、気候変動のような国際的な問題はイレギュラーで、経験や知識があるわけではない若者だからこそ問える危機感というのがあるのかなと。
久保田 そうですね。あと、自分には関係ないと線を引いてしまうのは、人権のような話にも通じると思います。大学で講義をした際に、人権というのは真っ当に生活している人にしか与えられないと思っている学生が一定数いました。
人権は生まれながらにして誰にでもあるものですが、たとえば犯罪者に人権はないという考えをもっている学生もいて。自分も該当するとは思っていない、裏を返せば、人権はあって当たり前と思っているのかもしれません。
日本の外に目を向けてみると、2022年7月、国連総会で、「清浄で健全かつ持続可能な環境に対する権利を人権として認める」とする環境権に関する決議(A/RES/76/300)が採択されました。2022年2月には、欧州委員会が「企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令案」(※注5)を公表しました。企業活動における人権、環境への悪影響を取り締まるもので、包括的な人権・環境関連リスクの特定とそれらへの対応を義務づける点では、今後、日本企業に与える影響も大きいと思います。ただ、人権と言われてどのくらい日本人に響くのか懸念もしています。
日本は、人権感覚というものが他国と比べて違うのかなと感じています。そのあたりを言語化していく必要がありますが、英語と日本語ではニュアンスの違いもあり難しいところです。
以前、法学の世界で英語の「right」をどう訳すかが議論になりました。訳語は「権利」ですが、日本ではそうした感覚が弱いのでうまく伝わらないのではないかと。自分に関わることには興味を持つけれど、そうではないと判断したら離れていく。このように、個人の根性というか意識に頼っていては危ういため、制度設計が必要だと考えています。
宮﨑 たしかに難しいところですね。
※注5 欧州の環境デュー・ディリジェンスについてはこちら
世の中のスピードにあわせつつ、信頼性をどう保つかーIPCCが直面している課題
久保田 IPCC報告書の執筆談に少し戻りますが、気候変動対策は今後10年が勝負とも言われており、世の中の流れも早まっている中、執筆作業ではその流れについていくのが大変でした。
第6次評価報告書では新型コロナやウクライナ侵攻など、気候変動対策に大きな影響を及ぼす問題について触れられていないという批判もありますが、世の中のスピードにあわせつつ、信頼性をどう保つかというのは今後のIPCCに問われていることでもあります。現実がどうしても先行していくので、それにあわせた制度づくりは一筋縄ではいきません。
宮﨑 以前対話オフィスが取材した、IPCCのセミナー(※注6)でも同様の点が指摘されていましたね。
※注6 IPCCを考察するセミナー報告記事はこちら
久保田 そうでしたね。パリ協定で定められた、長期目標の実現に向けて世界全体の気候変動対策がどれくらい進んでいるかを5年ごとに評価する、グローバル・ストックテイクというのがあるのですが、次の2028年までに第7次評価報告書を完成させることは、現実的に難しいとされています。(※注7)
IPCCの作業部会は「科学的根拠」「適応」「緩和」の3つに分かれており、学術的には綺麗な区別ですが、現実の政策ニーズに合っているのかという指摘もあります。さらに今後、(人間活動による地球温暖化は)「疑う余地がない」の次の表現はどうするのか、そして、もし1.5度目標を達成できなかったらどうするのか、なども頭の痛い話です。
宮﨑 1.5度は現実的に迫っている問題ですよね。専門家という立場は知見を提供するだけでなく、ときに現場との応答も求められると思いますが、今後の環境研究のあり方はどうあるべきか、意見があれば聞かせてください。
久保田 難しい質問ですね。昔と今では研究者の置かれている状況も変化してきていると思います。市民の声を聞く必要も生じており、試行錯誤しながらやっていくしかないのかなと感じています。社会との対話は時に手間がかかることで、目覚ましい成果がすぐに出るものでもなく、プロセスが重要ですよね。
様々な人の声を聞く体制づくりが求められていますが、一方でそれは全員がやるべきことでも、全員が得意なことでもないと思います。まずは、得意な人、あるいはやりたい人が試行錯誤しながらやっていくしかないのかなと。いきなり社会が変わることは難しいので、一つ一つ変えていく必要があります。
※注7 2025年2月、IPCC第62回総会(杭州(中国))において、第7次評価報告書の章構成には合意しましたが、タイムラインについては3回目の先送りとなり、第63回総会(2025年後半にペルーで開催予定)へ先送りされました。
将来世代の権利をどう考えるか―これからの法学研究者に求められること
宮﨑 何事も一朝一夕にはいかないですね。久保田さんは廃棄物の問題から始まり、はじめは興味がなかった温暖化をふくめ、現在は将来世代を考える研究「Beyond Generation」プロジェクト(以下、BGプロジェクト)(※注8)にも参加していると聞いていますが、どういう思いで研究していますか?
※注8 「Beyond Generation」プロジェクトの詳細はこちら
久保田 法学の世界では、長期的に物事を考えることを前提にしていないところがあります。BGプロジェクトでは世代間衡平性の問題が主題の一つにあるのですが、この議論は90年代くらいから出てきたもので、歴史としては長くないんです。
法律や法学は、基本的に現在世代を対象にしているので、まだ生まれていない世代の権利や利益を考えることは重要だという認識はありつつも、現在の制度とどのように結びつけるかは難しいところがあります。また法学の中で「権利」というものは扱いが重いもので、迂闊に使えないといった点もあります。
たとえばカーボンプライシング(※注9)の手法のひとつに「排出量取引」(emission trading)がありますが、アメリカでこの制度が導入された頃は、日本では「排出権取引」と訳されていました。それに対して、「権利」とすると何かあったときに補償をしないといけなくなるので、適切ではないという指摘がありました。原語には、もともと「権利」という語は入ってませんし、米国内の議論でも権利性は否定されているので、少なくとも法学者が訳したものではないはずです。
ただ、法学者はこれまであまりにも「権利」ということを言ってこなかったから、将来世代の権利まで拡張して考えることができていない側面もあると思います。世界人権宣言では「人は生まれながらにして」と書いてありますが、そもそも生まれていない人のことは考えていないわけです。しかし、今は存在していなくてもこれから生まれてくる世代が温暖化した世界に生まれたら困るのもたしかで、それを理屈づけ、理由づけすることは、たしかに法学研究者の仕事として求められるものだと感じています。
※注9 カーボンプライシングとは:企業などの排出するCO2(カーボン、炭素)に価格をつけ、それによって排出者の行動を変化させるために導入する政策手法のこと。
宮﨑 私は環境活動をする中で、若者世代としての「権利」を主張してきたところがありましたが、権利に対する見方は多様であるというお話はとても新鮮でした。
久保田 そうですね。法学以外の研究者は、わりとカジュアルに「権利」というワードを使っていると感じます。でも権利と言わないと、本来ならあって然るべきことまで抑圧されてしまうのも確かなので、主張することも大事だと思います。
宮﨑 なるほど。本日は環境法からはじまり、現世代と将来世代の権利まで興味深いお話をありがとうございました。
<対談を終えて>
個人の根性に頼る環境改善は続かない、という冒頭のエピソードが印象的でした。日本では人権意識が弱く、現場の声を重んじる傾向があるという点も、環境法を専門とする久保田さんの言葉で語られることで、法に基づく制度づくりがだからこそ重要であるということが説得力をもって響いてきました。
一方で、現在ある法律は基本的に今の世代を対象にしており、将来世代のことを考えられていないというお話もあり、俯瞰的な視点で法学の世界を知ることができました。久保田さん、ありがとうございました!
[掲載日:2025年7月17日]
取材協力:国立環境研究所 社会システム領域 久保田泉主幹研究員
取材、構成、文:宮﨑紗矢香(対話オフィス)
参考資料
●国立環境研究所 地球システム領域「地球環境研究センターニュース」
https://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201506/295002.html
●株式会社日本総合研究所「欧州の人権・環境デュー・ディリジェンス義務化と日本への示唆 」(外部リンク)
https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=104747
●国立環境研究所 社会システム領域「脱炭素・持続社会研究プログラム」
https://www.nies.go.jp/social/research/dssrp.html
【連載】ミヤザキが行く!研究者に“突撃”インタビュー
●Vol.02:田崎智宏さん(資源循環・廃棄物管理の専門家)
●Vol.06:番外編①「IPCC」を考察するセミナー報告記事
●Vol.06:番外編②Kari De Pryckさん(科学技術社会論の専門家)
●Vol.09:HARTWIG Manuela Gertrud(ハルトヴィッヒ・マヌエラ・ゲルトルト)さん(社会学の専門家)