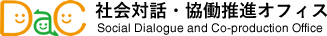【連載】ミヤザキが行く!研究者に“突撃”インタビュー
-教えて高木さん!化学物質の人へのばく露を研究しているのはなぜ?リスクや健康について思いをめぐらせながらお聞きします
連載「ミヤザキが行く!研究者に“突撃”インタビュー」。インタビュアーは“ミヤザキ”こと、宮﨑紗矢香です。
環境研究の研究者ってどんな人?どんな社会を望んで研究しているの?背景にある思いなどをミヤザキ目線で深堀りし、研究、人柄の両面から紹介します!
Vol.11:高木麻衣さん(ばく露科学の専門家)

第11回のゲスト研究者、高木さん(右)と筆者。ニホンザルが好きだそうで、サルグッズがいっぱいです。
洗剤、甘味料、農薬、化粧品etc...私たちの身近にある化学物質は、便利な生活をもたらしてくれる一方で、人の健康や生物に悪い影響をおよぼすことがあります。日本では高度経済成長期に公害問題が深刻化し、そのリスクがクローズアップされましたが、近年も有機フッ素化合物(PFAS)など、人体への作用が不確かな化学物質は多く存在しています。
今回は、人の健康と環境化学物質のばく露に関して研究を行う高木さんにお話を伺います。リスクと健康の分野でさまざまな調査に携わる高木さんの、研究にかける思いとは?
連載のバックナンバーはこちら
Vol.01:江守正多さん(地球温暖化の専門家)
インタビュアー:宮﨑紗矢香
対話オフィス所属、コミュニケーター。大学時代、環境活動家グレタ・トゥーンベリさんのスピーチに心を動かされ、気候変動対策を求めるムーブメント、Fridays For Future(未来のための金曜日/以下、FFF)で活動。
地球を救おう!でもどうしたら人を動かせる?思い浮かんだのは「人の健康」
宮﨑 専門は「ばく露科学」とのことですが、なぜこの分野の研究を志すようになったのでしょうか。まずは経歴を教えてください。
高木 そもそも環境問題に興味を持ったのは小学生のときでした。テレビや漫画で海の問題や森林破壊、二酸化炭素などのキーワードを目にし、地球を救おう!と漠然と思っていました。環境省の“こどもエコクラブ”にも入っていました。実は、刑事ドラマを見て警察官に憧れたこともありますが、身長が足りず早々にあきらめました(笑)。世の中をよくしたいという正義感という意味では共通しているかもしれません(笑)
大学では森林資源学や環境汚染化学を学んでいましたが、問題解決に向けてどうしたら人を動かせるかと考えたときに、身近なテーマで「人の健康」というのが思い浮かびました。それから、大学院では化学物質の人へのばく露といったテーマを扱うようになりました。
専門のばく露科学というのは、人がどんな化学物質をどのぐらい取り込んでいるのか、どういう経路から取り込んでいるのかを調べる学問です。人はいろいろなものから化学物質を取り込んでいますが、取り込んでいる量(ばく露量)を推定するのがばく露評価で、その量が健康に影響を及ぼしうるのか、その可能性はどのくらいかを評価するのががリスク評価です。私はその中でも、主にばく露評価に関する研究をしています。普段、私たちが吸っている空気や家のほこり、食べ物、あるいは肌に塗る化粧品なども研究対象です。
宮﨑 人の健康というテーマはたしかに身近ですね。もともと大学では何を研究されていたのでしょうか?
高木 大学時代の研究室のテーマは土壌学でした。「窒素過剰」という、川などに窒素やリンが過剰に流れ込み、地下水を汚染する問題を調べていました。
私は静岡県出身なのですが、名産品のお茶は美味しくするために窒素肥料がたくさん入れられている(た)そうなんです。しかし、肥料を過剰に与えたことで地下水の窒素汚染を招いたという話を聞いて、静岡県民として気になったのがきっかけです。
学部時代は化学に加えて、林業なども幅広く学んでいました。分析が好きだったので、最終的には環境汚染化学分野に進みました。
宮﨑 私は化学方面になじみがないので新鮮です。昔から研究者になりたいという気持ちはありましたか?
高木 特にはなかったです。就職活動もしましたが、大学院で研究するうちに楽しさが勝り、もう少し続けたいなという気持ちで博士課程に進みました。その研究を国立環境研究所(以下、国環研)と一緒にやっていたこともあり、ご縁があって研究員として雇っていただきました。
それから東日本大震災が起きたのですが、放射性物質のばく露に関わる職員の募集があり、ばく露科学を専門にやっていたので応募してみたところ、国環研の福島地域協働拠点(以下、福島拠点)に行くことになりました。福島には5年ほどいました。
住民の方が安心して暮らせるように。福島での放射性物質の研究と地域との協働
宮﨑 福島拠点でも様々な研究をしていますよね。浜通りの山間部に位置する飯舘村で、大気中やハウスダスト(家屋内のほこり)の放射性セシウムのモニタリングを続けてきたと聞きました。また、野生の山菜やキノコへの放射性セシウムの蓄積特性の解明も行っているんですよね。
高木 放射性物質の研究は、森林や田んぼ、畑など外部環境が対象になりますが、人は基本的に家にいるので室内環境も重要です。ハウスダストは呼吸器から取り込むこともありますが非意図的に食べてしまっているものもあり、それがさまざまな化学物質のばく露源になっています。そのため放射性物質の場合も、ハウスダストからどれぐらい取り込んでいるかを推計した方がよいのではないかということで、研究を始めました。
月に1回ほどの頻度でハウスダストを持ち帰り、放射性物質が減っているかを見たり、現場を訪問して床面や天井裏にどのくらい分布しているかを測定したりしました。放射性物質が体の内部にあり、体内から被ばくすることを「内部被ばく」と言いますが、リスクが懸念されるほどの量ではないとしても、住民の方が安心して暮らせるようにという思いで研究してきました。
今は山菜の放射性セシウム濃度の調査をしています。福島の方々にとって山菜は単なる食料ではなく、食文化であり、採って加工して食べて楽しむものでした。それが原発事故の影響で、山菜に出荷制限がかかり、楽しみが奪われてしまったんです。山菜を楽しめないなら、ふるさとに戻っても仕方がないという声も聞かれます。少しなら食べている人もいるし、汚染されているから絶対に食べないという人もいます。いずれにしても、食文化の一つとして切り離せない存在だった山菜を安心して食べてもらえるように、福島拠点チーム一丸となって調査をしています。
宮﨑 被災地では、研究者としてどんな心持ちで現地に入りましたか?
高木 最初は初めて行く場所だったので、まずは現状がどうなっているのか知りたいという気持ちでした。研究者に対してさまざまな感情を持っている方もいるというお話もお聞きしましたが、研究者に関わらずいろいろな人に地域に来てもらいたいとおっしゃっていたのが印象的でした。
私たちは、調査した環境データをお伝えし、住民のみなさんが暮らしていく上での安心材料にしてもらいたいという思いで、私たちができることを少しずつ、「対話」を大事にしながら研究を進めてきたつもりです。

福島にてフィールドワークを行う高木さん
宮﨑 放射性物質のモニタリングや山菜の調査は、住民の方と一緒に行っていると聞きました(※注1)。研究者が独自にデータをとって伝えるより、データへの信頼性も高まると。
※注1 環境儀No.80「災害環境研究のこれまでとこれから」(7頁より)は、こちら
高木 はい。「福島地域協働拠点」というように、まさに「協働」ですね。地域の人々と一緒に調査をする重要性は感じています。
人によって異なるリスク認識。研究者として数値基準を示し、正しく伝える難しさ
宮﨑 ところで、先ほど出てきた「リスク」という単語について、私たちは何気なく使っていますが、さまざまな意味をはらんでいると思います。過去に受けた大学の講義で、リスクに対してどのような選択をするかは個人にゆだねられているものの、現実にはリスクをめぐる決定は集合的に行われており、個人だけで完結できない社会文化的なものだという話を聞きました。被災地でもリスクは大きなテーマだと思いますが、研究される中で考えてきたことはありますか?
高木 リスクは可能性(確率)です。リスクは“ありかなしか”ではなく、ある量のばく露を受けることによって影響がどの程度増えるのか 、何倍になるのかという議論を行います。リスク管理においては数値的な基準を作りますが、人それぞれ許容できる範囲は異なります。同じ状況に置かれたときにある人はこのリスクを受け入れられるけど、ある人は受け入れられないということも出てきます。おかれた原因や状況によっても変わるかもしれません。
リスクを減らすためには、リスクとなる要因から離れるのも一つの選択ですが、それができない人もいる。そうした人々のために、我々としてはリスクをなるべく下げる研究をしたいと思っています。
宮﨑 福島第一原子力発電所にたまる処理水の海洋放出をめぐって議論が生じた際にも、国際原子力機関(IAEA)は「国際安全基準に合致」しているとして海洋放出を評価(※注2)していましたが、住民や漁業関係者は納得できないといったやりとりがありました。また、新型コロナの際もリスク管理の話が飛び交い、情報を受け取る人の立場や考え方、価値観の違いが浮き彫りになった気がします。
※注2 経済産業省「みんなで知ろう。考えよう。ALPS処理水のこと」のページはこちら
高木 情報を伝えるのは難しいですね。安全性を示す基準として出された数値だけを見て納得いかないこともあると思うんです。研究者ができることは科学的に正しく伝えることですが、ただわかりやすく数値を伝えるだけでは十分ではありません。そういう背景もあり、福島拠点では研究者が勝手にデータを出すのではなく、住民の方と山に入ってデータをとるなど、一部だけでも一緒にやるプロセスを大事にしています。
宮﨑 これは私の印象ですが、ばく露科学の研究は実験室にこもって行うイメージがあり、それに対して福島での調査は現場に出ていって、現地の人とやりとりしながら行う、質の異なる研究のように感じました。
高木 ばく露科学といっても人を対象にした研究なので、自宅を訪問して試料をもらうというやりとりはあります。しかし、我々の計画した研究内容に沿って行うことが基本です。福島の研究では、住民の方とコミュニケーションをとりながら、どういうことが不安で、どういうことを知りたいのかを聞きつつ、いただいたご意見を研究に活かしていくところが大きく違う部分ですね。
人も生物も健康に生き続けるため。環境基準を出し、化学物質を適正利用する研究の意義
宮﨑 ところで、高木さんは「子どもの健康と環境に関する全国調査(以下、エコチル調査)」にも携わっていますが、どんな研究をしていますか?
高木 エコチル調査は、日本中で10万組の親子に参加していただく大規模な疫学調査(※注3)で、環境中の化学物質が子どもの健康にどのように影響するのかを明らかにすることを目指しています。エコチル調査に携わっている700名くらいの研究者や医師らがエコチル調査で得られたデータを使って論文を書くのですが、同じテーマで論文を書きたい人が複数人いることもあり、テーマが重ならないように調整をしたり、論文執筆を促したりしています。
そのためデータを使った研究というより、エコチル調査の成果発表や広報などの運営部分を担当しています。環境省主催のシンポジウム(※注4)では芸人さんと一緒にサブ司会もやらせてもらいました。
※注3 疫学調査とは、集団を対象として、病気の頻度、その分布に影響する因子を統計学的に研究する学問。
※注4 第14回エコチル調査シンポジウム特設サイトはこちら
宮﨑 司会進行の様子を録画で見ましたが、すごく自然でしたよね!高木さんはエコチル調査のどんなところにやりがいを感じますか?
高木 世界的にも類を見ない大規模な疫学調査なので、化学物質だけでなく医学的にも社会的にも、貴重な情報がたくさん得られています。世の中をよくすることにつながるような調査に携われているのは嬉しいです。ご協力いただいている参加者のみなさんにも感謝しています。
宮﨑 ここまで話を聞いて、高木さんは「人の健康」という一貫したテーマで研究を行っていると感じました。冒頭の、地球をよくしたいという幼い頃の思いは今も変わらないですか?
高木 変わらないですね。綺麗な地球がずっと続いていくことを願っています。人も生物も植物も動物も健康に生き続けられること、綺麗な空気、海、森林が守られることが一番の目標です。福島拠点の研究でもエコチル調査でも、人の健康を守るためのリスク管理(例えば基準値の設定)に不可欠な科学的証拠を集めているわけですが、化学物質を適正に利用することにつながります。それが、ひいては生物を守ることにもなると考えています。
宮﨑 たしかにそうですね。とても大事な研究だと思います。ちなみに高木さん自身は、私生活で健康に配慮していることはありますか?
高木 食べ物には少し気を遣っています。科学的に考えて問題ない量は食べますが、食べ過ぎないようにしている食べ物もあります。
食塩、糖分といったものもそうですが、たとえばマグロやひじきがあります。マグロのような大型魚類には神経毒性のあるメチル水銀が、ひじきには発がん性がある無機ヒ素が、比較的高い濃度で含まれています。1日あたりの摂取がこれ以下にしたほうがよいという量が設定されています。海藻類や魚介類には、必須ミネラル、オメガ3脂肪酸などもちろん健康によい成分も含まれているので、リスクとベネフィットの考え方にもとづいて判断しています。
あとは山の中を走るトレイルランニングというスポーツを少しやっていて、トレイルランにしては短めですけど10-30kmくらいのレースにも出たことがあります。山を走るのはかなり苦しいし、全然速くもないのですが、きれいな自然や景色に出会うことができて楽しいですし、体力保持にも貢献しているのかなと思います。

富士山麓にてトレイルラン中の高木さん
宮﨑 少し!?長距離走が苦手な自分からしたらとんでもない距離です!改めて本日はお話ありがとうございました。
<対談を終えて>
高木さんのお話を聞くまで、化学物質の健康影響というテーマをあえてじっくり考えることがなかったため、自分の無頓着さと無知を思い知らされると同時に、ばく露科学や放射性物質、リスク管理の話は、人が安全に暮らしていく上で重要な研究分野だと感じました。
同じように地球を救いたいと思っても、気候変動を軸に考える自分と異なり、人を動かす導線として健康に目を向けるという高木さんの視点は、興味深くもありました。近年は気候変動も、暑熱リスクや気温上昇による疲労感など健康に直結する問題となりつつあり、環境や健康といった言葉が包摂する射程が広く多様になってきていることや、時代の進展とともに環境研究も分野横断で考えることが求められているように感じました。高木さん、ありがとうございました。
[掲載日:2025年7月31日]
取材協力:国立環境研究所 環境リスク・健康領域 高木麻衣主任研究員
取材、構成、文:宮﨑紗矢香(対話オフィス)
参考資料
●国立環境研究所(2021/3)『環境儀』 No.80(PDF)
https://www.nies.go.jp/kanko/kankyogi/80/80.pdf
●経済産業省 みんなで知ろう。考えよう。ALPS処理水のこと「IAEA包括報告書 国際機関によるALPS処理水海洋放出の安全性確認」(外部リンク)
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/shirou_alps/reports/02/
●第14回エコチル調査シンポジウム(外部リンク)
https://www.env.go.jp/chemi/ceh/results/2024/14th_symposium.html
【連載】ミヤザキが行く!研究者に“突撃”インタビュー
●Vol.02:田崎智宏さん(資源循環・廃棄物管理の専門家)
●Vol.06:番外編①「IPCC」を考察するセミナー報告記事
●Vol.06:番外編②Kari De Pryckさん(科学技術社会論の専門家)
●Vol.09:HARTWIG Manuela Gertrud(ハルトヴィッヒ・マヌエラ・ゲルトルト)さん(社会学の専門家)