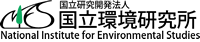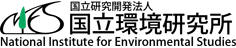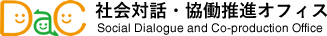2017年度所内ワークショップ報告
「メディアとの上手なつき合い方」
はじめに
社会対話・協働推進オフィス(以下、対話オフィス)では、国立環境研究所(以下、国環研)の研究所員を対象に、『対話』に関する経験の共有、そして『対話』について興味がある研究者への情報提供や支援を目的に、ワークショップを毎年開催しています。
今年度は「メディアとの上手なつき合い方」をテーマに、3月1日(木)に実施しました。
研究所、研究者にとって、メディアは研究成果や活動を発信する手段のひとつであり、また社会の関心を知り、一般の方と交流する大切な回路でもあります。
ですがその一方で、研究者が伝えたいこととメディアが伝えたいことがうまく折り合わず、実際に発信された内容が望んでいた形とはかなり異なったりするという難しい点もあります。
社会に情報をうまく伝えるためには、記者とどのように向き合い、どんな心構えを持つべきなのか?
国環研の中でもメディア対応の経験が豊富な研究者3名と、またメディア側から新聞記者2名の計5名が登壇し、パネルディスカッション形式でそれぞれの経験談や事例、そしてメディア側の仕組みや事情などを紹介しました。
参加いただいたパネラーは、以下の5名の方たちです。
・亀山康子 副センター長(社会環境システム研究センター)
・五箇公一 室長(生物・生態系環境研究センター)
・林誠二 研究グループ長(福島支部)
・大塲あい 記者(毎日新聞)
・冨永伸夫 元記者(対話オフィス/元朝日新聞)
ほかに、当日は欠席となりましたが、菅田誠治 室長(地域環境研究センター)からも事前に経験談をヒアリングしました。
進行は対話オフィス代表の江守正多が務め、約40名の研究所員が参加しました。
所内のイベントではありますが、より多くの方にご参考にしていただきたく、ワークショップでの議論のポイントと当日の様子をご報告させていただきます。

当日の会場の様子。ワークショップの概要を説明する江守さん。
研究者のメディア対応における『心得』とは
今回のワークショップでは、国環研の広報研修で以前に使用されたメディア対応に関するガイドラインを最初に紹介してから話を展開しました。一般的にはこうやって対応するようにと説明されているが、実際はどうなのか、違いはあるのか。
各パネラーがそれぞれ研究者、メディアの立場から経験談、ノウハウ、実情などを紹介し、その後、実際に所内の研究者が持っているメディアへの疑問や対応方法の是非について話し合いました。
その中から要点として得られた、メディア対応における『心得』は以下になります。
一、まず、取材者が、その取材テーマにおいて初級者か上級者かを見極めよう
一口に記者といっても、専門記者、記者クラブ詰め等の上級者と、そのテーマを初めて取材しにきた初級者がいる。
一、初級者に対しては、枝葉(細かい部分)は話さず、幹(話の大筋)だけを説明しよう
初級者に枝葉を話すと消化しきれずに混乱してしまい、幹さえもうまく伝わらない。
一、特に初級者の質問には、できるだけ『はい』『いいえ』『わからない』がはっきり伝わるように答えよう
重みを付けずに両論を話すと、自分の意図しない結論が記事になってしまうことも。
一、取材者に専門外のことも聞かれる機会が増えてきたら、答えられるように勉強しよう
狭い専門領域を超えて、そのテーマのスポークスパーソンの役割を果たす人が必要。
一、不慣れな研究者が取材を受ける場合は、一人で受けない、録音をするなど、周到に対応しよう
取材時の発言をうまくコントロールし、もし後でトラブルになっても対処できるように。
一、新聞記事の原稿は、原則的には確認不可だが、確認できる箇所がある場合もあるので、取材者に聞いておこう
「」付きでコメントが紹介される場合など、表現を確認させてもらえることがある。
ここからは、この『心得』を得るにいたったワークショップの内容を詳しくご紹介していきます。
パネラーの経験談や実例紹介
研究者の視点から
トップバッターは、気候変動に関する国際制度などを研究し、COPでも活躍されている亀山副センター長。
メディア出演は、環境問題に少しでも多くの方に関心を持ってもらうための大切な手段と考え、特に、普段から環境問題にあまり関心のない人たちへ発信される媒体、内容のものは優先的に引き受けようと努めているそうです。
取材を受ける際、亀山さんが特に気を付けていることは、先方についてよく理解し、できるだけニーズに応えた対応をすること、そして、よりわかりやすくメッセージを伝えること。
「取材者側がどういう目的をもって、どんなターゲットに向けて発信したいのかをきちんと確認して理解し、できるだけそれに近づいた形で対応できるよう時間を割いて準備している」と話します。
また、取材者のこの分野における専門知識レベルを理解して、初級者の方には大筋となる幹の部分だけを話し、あえて細かい枝葉的な話は省略することで、聞いている側が混乱しないように情報を伝えるそうです。
また、亀山さんはメッセージをわかりやすく伝えるために、「取材の方は、色々聞いたあとで『結局、温暖化は危ないんですか?』など、そうかそうでないかの判断を確認したがるもの。
そういう時に、情報は渡したので判断はそちらで、みたいな言い方をするとやっぱり弱く、研究者としては踏み込みすぎかもしれないが、あえて私は『はい』『いいえ』ときっちり言うように心がけている。
また、話を理解しやすくするために具体例もできるだけ多く準備する」と、取材対応へのノウハウを話しました。

亀山康子 副センター長(社会環境システム研究センター)。
東日本大震災以降、被災地の環境回復と創生に向けた災害環境研究を目的に開設された福島支部の林研究グループ長は、放射能汚染問題へのメディア対応で苦労した経験談を紹介しました。
以前、対話オフィスのコラム記事(※注1)でもご紹介しましたが、福島のダム湖に放射性セシウムが溜まっており、将来的リスクがあるという新聞記事が出た時の話です。
林さんは取材の時、記者の方に「(ダム底の放射能を)取り除く作業に伴い再汚染や経済的負担のリスクがあるため、当面は何もしない方がいいけれど、将来のリスクの検証はするべきだ」と、取り除いた時、取り除かなかった時の両面から話をしたはずなのに、結局記事では一方だけ、取り除かなかった時のリスクの話だけを林さんの発言として取り扱われてしまいました。
では、どうしてこのようなことが起きてしまったのでしょうか?林さんはこのときの問題について、一番まずかったのは「取材に対して無防備であったこと」と分析しています。
取材は記事が出される2か月前に行われ、もともとは福島の現在の汚染状況について、そして今後について理解したいのでレクチャーをしてほしいとの依頼で受けたとのこと。そのため、当日は記者の方も録音などはせず、ノートにメモを取りながら話を進めました。
雑談のように、時おり除染体制への不満も交えながら話をした結果、記事では刺激的なところだけをうまく拾われて使われることになってしまったのです。
それ以外の反省点として、取材時に録音をしなかったこと、相互に発言がコントロールができるように1人ではなく複数で取材を受けるべきだった、今回の件について言えば記事が出る前にある程度の概要(どういった趣旨で記事が書かれるのか)を確認できればよかったといった点も挙げてくれました。
一方で、「事故から5年が経ち、ある意味この問題(放射能汚染)が社会的にも風化していく中、掲載された記事自体に意義はあったと今でも思っている。
だからこそ、なぜ、科学的事実に基づく内容ではなかったのかというところが非常に残念」と、メディア側と研究者側が伝えたいことのギャップへのジレンマについても話しました。
※注1 対話オフィスのコラム記事はこちら

林誠二 研究グループ長(福島支部)。
新聞や雑誌以外にも、バラエティ番組に出演するなど、当研究所の中でも特に多ジャンルで活躍する保全生態学者の五箇室長。さまざまな経験を通して、メディア出演の際には日ごろから心がけていることがあると話します。
「先ほど亀山さんが話した、できるだけ『はい』『いいえ』で答えるということは、逆に言うと、不確かなことは『わからない』『不確かです』と答えることも大切だということ。また、記者のペースには乗らないというのもすごく重要で、できるだけこちらのペースに乗せるという話術も必要だと思っている」と、独自のノウハウを教えてくれました。
また五箇さんが苦労された点としては、記者や番組製作者側の裏取り不足を挙げました。
新聞の場合は、記事が出る前の晩など直前に連絡が来ることも多く、確認できなかった場合にはそのまま記事になってしまうこともあります。またテレビでは、出演した番組内で放送された映像の確認までしておらず、放送後にクレームを受けたこともあったそうです。
これらの経験から、テレビに関しては映像まですべてチェックするように気を付けているとのこと。新聞などは確認できないことも多く、媒体としての特性を理解した上で、それでも取材を受けた側に記事の掲載時期や不確かなところは確認をする必要があるのでは?と、メディア側への問題点を指摘しました。
また、研究者として一番大切なことは、「1回や2回のミスでも動じないだけのバックグラウンドを維持すること。学術界ではきちんとした研究者として認められているという研究成果を常に維持することも、われわれ国の研究機関に務める者としての義務であり、責任であると思っている。
テレビに出ることが仕事ではなく、科学者として科学的な知識を提供するためにテレビを利用するというスタンスも、われわれは維持しなければならない」と、メディア対応における心構えを話しました。

五箇公一 室長(生物・生態系環境研究センター)。
今回スケジュールの都合でワークショップには参加できなかったのですが、PM2.5が日本で問題になり、それ以降メディアからの問い合わせに試行錯誤しながら対応してきた地域環境研究センターの菅田室長からも事前に経験談をもらい、モデレーターの江守さんが代理で紹介しました。
菅田さんが特に苦労したのは、自分の専門分野外について聞かれること。自身は大気(PM2.5でいうと、大気中の輸送や拡散、濃度の変化など)が専門になるのですが、取材に来る多くの方から、PM2.5の人への健康影響についてコメントを求められたそうです。
専門外の内容については、知っている範囲(一般的な内容や専門家から聞いた話など)で答えるように対応しているそうですが、そこだけが使われてしまうことへの居心地の悪さや違和感を覚えることもあったと話してくれました。
また、取材でいろいろ話をした後に、記者の方が内容を理解した結果、心配することではなかったと判断して、実際に記事にならなかったケースもあったとか。
メディアとの間にきちんと対話が成立し、一緒に考えることができた成功例として挙げてくれました。

菅田室長の経験談を説明する江守さん。
メディアの視点から
では、メディア側の見方はどうなのでしょうか?
毎日新聞で科学、医療、環境省、文部科学省などを担当している大塲記者は、いわゆる“科学記者”と呼ばれる、分野に特化した専門記者です。
大塲さんが研究者に取材をお願いするケースとしては、研究発表や論文のプレスリリースをもらい内容を詳しく確認するためというパターンが一番多く、その他には、その時々で注目が集まっているテーマについての現状や意見を聞くため、新聞の特集欄の取材のため、または勉強のため研究者に話を聞きに行くこともあるそうです。
また、研究者がメディアに対してギャップを感じていることや、言いたいことが伝わらなかったり、表現が変わってしまうことなどへの疑問については、新聞という媒体の性質的な難しさがあると話します。
新聞はあくまで一般の方が読むものなので、一般的に興味を持ってもらえるポイントを押さえ、気軽に理解できるわかりやすい言葉を使うことが最も重要視されるそう。
「聞いた内容をわかりやすく噛み砕いて記事にするため、研究者の方の中でも、どうしてこの言葉が新聞でこう言い換えられるんだと思っている方もいると思う。
しかし、われわれもここまで言い換えていいものなのか、それは日々上司、同僚と議論しながら、ここまでならと、常にギリギリの線をさぐりながらやっている」と、メディア側の葛藤について話しました。
その他にも、掲載ページ数が限られていること、さらに読者層の高齢化にともない活字の拡大、イラストや写真の多用などで文字の情報量が減る中、いかにスペースを確保するかといった現実的な問題も大きいと話します。
そのため、見出しの文字数が減ることで、特にセンセーショナルだったり、簡単な表現が優先されてしまうなど、新聞社が抱えている現状の問題について紹介しました。

大塲あい 記者(毎日新聞)。
現在は対話オフィスのスタッフで、定年退職まで朝日新聞に勤めていた元記者の冨永さんは、いわゆる“記者”という職業や分類がどういったものかを話しました。
新聞記者といっても、大塲さんのように担当分野が決まっている専門記者もいれば、社会部の所属が長かった冨永さんのように、さまざまな分野を取材する非専門記者がいることを説明しました。
国環研に取材をする記者は、おそらくは専門記者が多く、環境省の記者クラブで情報を得て、その情報をより深く掘り下げるために調べたり、環境省に確認する中で研究者へ行き当たるという流れがあるそうです。
メディアである以上、特ダネを発掘するのが一番の仕事になると話す冨永さん。でも、専門記者の場合、専門的な知識も豊富で、より状況を理解している一方、どうしても役所の立場を理解しすぎて独自性のない記事になってしまう傾向があるとも話します。
「そうなるとどこの新聞でも同じ紙面になるというフラストレーションが発生してしまうが、そういう時に、非専門記者は噂やネット、市民団体の発表など、さまざまなところから疑問を持って自分でリサーチして取材を始めるので、独自色に富んだ素晴らしい記事が生まれることがある」とその多様性を紹介。
しかしその一方で、リサーチ不足や思い込みにより、おかしな記事になって結局は批判を浴びてしまうといった危険性についても話しました。

冨永伸夫 元記者(対話オフィス/元朝日新聞)。
質疑応答で、さらに詳しく意見交換
大塲さん:毎日新聞では基本的に、裏が取れない記事というのは、書けないし載せられない。例えば、確認を取りたい研究者の方に連絡が取れなくて裏が取れないとなったら、裏が取れるまでいろんな人に連絡して、それでも取れなかったらひっこめたり。
処理対応としては、取れるまで努力するしかなく、原則として裏取りは強く言われている部分でもある。
冨永さん:原則的には、大塲さんがおっしゃったように、裏取りができない場合にはひっこめる。
でも事前の取材が十分だと判断でき、なおかつその証拠が自分のノートにきちんと残っていて、記事を書く段階で先方に改めて確認を取らなくても十分だと判断できれば、そのまま記事として出している。
亀山さん:先ほどは、できるだけニーズに応えた対応をするとお話ししたが、取材の質問を聞いた上で私のポリシーと違うと思ったら、私にはできませんとはっきり答えるようにしている。
この線は譲れないときちんと先方にお伝えした上で、それでも私でいいのか、またはそういう内容ならこの方がいいのではと、別の方を推薦することもある。
五箇さん:使われなかったらあきらめる。僕自身、テレビとの付き合いも長いけど、うけなかったら使われないっていうのは仕方がないし、自分の意見と違うと思ったのなら言わないのが正しい姿勢だと思う。
林さん:科学的事実に基づいて判断し、それはおかしいとなったら答えないのは仕方ないと思う。
でも一方で、さっきの両論の話じゃないけど、科学的事実に基づいて可能性があるのであれば、私だったら両方の話をするかな。もしそれで片方しか使ってもらえないとしても、聞いている人への対応としては真摯じゃないと思うので。

亀山さん:両論がある時は、それを50:50で話すのではなく、どちらかにウェイトをつけるようにしている。
取材者がこの分野において初級者か上級者かによっても違うが、上級者は両論を話すとけっこう正しく理解してくれるが、初級者の場合は混乱することがある。なので、あえてちょっと大げさ目にどちらかにウェイトをつけているが、リスクはあるとも思っている。
例えば、「異常気象がたくさん起きている、これは温暖化が原因なのか?」と聞かれた場合、すべて説明しようと思ったらとても複雑で長くなる。以前ラジオ出演した際には、「言い切れないけれど、頻度が高まることについては科学的にほぼ正しい」といった具合に、一言にまとめて伝えたことも。
異常気象は温暖化が原因で増えている可能性が高いというニュアンスを含めつつ、言葉を選びながら話すようにしている。
五箇さん:両論あるってことは、まだわかってない、要は不確定であるとも言える。なので、そういった場合には不確定ですねとしか言えない。わからないの方を強調するというよりは、まだ決定は出てないという形でしか言わない。
僕が対応しているテーマについては、だいたいそういうものしかないので、わかんないことはわかんないとしか言わないようにしている。
林さん:対象とする問題によって異なるとは思うが、例えば五箇さんが専門としているヒアリなどは、明らかに危ないと言える。
でも放射能の話は、確かにそういう部分はあるかもしれないけど、現状として汚染の程度によっては震災前と同様に生活している人たちがいる環境なので、必ずしも危ない状況でもない。そういうことを考えると、断言することが難しいことも多い。
先ほどの記事の取材の時も両論を伝えたし、私の意見としてはダム湖に溜まったセシウムはそのままにしといた方がいいと、かなり強調して言った。だからこそ、逆側の記事に出てしまって、なおさらショックだった部分もある。
受け取る側がどう取るかによって変わってくるので、受け手がどのくらいの理解力がある人なのかの把握が、私にはちょっと足りなかったのかなと思う。
大塲さん:記事を書く上では、それがそのまま見出しになることもあるので、『はい』か『いいえ』かはっきり言ってもらった方が有難い。
ただ東日本大震災以降、いろいろと悩みながらやっている中で、「わからないことはわからない」ということを、ちゃんと載せていく新聞も作っていかなければならないのではという議論は社内でもするようにしている。
亀山さん:私は専門外の内容でもできるだけ答えるようにしているし、これは喋れば喋るほどうまくなっていくものなので、取材回数が増えるほど自分が熟練していく部分でもある。上手く答えられないと悔しくて、その晩家で一生懸命調べてみたり。
こういったものは失敗の繰り返しなので、今後取材を受ける可能性がある方は、最初は言えることが少ないかもしれないが、こういった経験を通して言えることを増やしていってもらえたらと思う。
また、「勉強しに来た」という感じの取材者には、専門家を紹介するようにしている。他の人のところまで取材に行かなそうな人であれば、自分が知っている範囲で答えてあげる方が良いと思う。
五箇さん:テレビ出演などで生物のことなら何でもみたいなキャラクターになってくると、今ではいろんな雑学の引き出しを増やして、だいたい答えるようにはしている。
良かれ悪しかれ、僕の場合はメディアを通してずっと訓練してきたというのがあるので、大概のことには答えられるようにしているけど、逆にそれを超えてわからないことは、さすがにそれはわかりませんと言い切っている。
わからないことでも専門の方が誰かは一応知っているわけだから、だれだれ先生に聞いていただければとサジェストするようにしている。
林さん:取材までに時間的余裕があれば、調整して質問の内容を想定し、他の専門の研究者にも同席してもらったりしている。
時間がない場合には、自分の知り得る限りの情報で対応し、納得してもらえなかった場合には、より詳しい人を紹介している。
冨永さん:新聞記者としては、自分たちが書いた原稿とか作っている紙面を新聞として世に出す前に外部に出すということは、やってはいけないと教育されている。
見せるということは、直すということを前提にして見せることになるので、そうなると検閲という問題に発展してしまうことも。
ただケースバイケースな部分もあり、専門性が高い分野において、数値があっているのか、その数値の意味はどうなのかといった事実確認については間違えてはいけないので、そういった部分は確認をする必要があると思うし、取材対象のコメント部分については、その意味合いを確認してもらう作業が必要な場合も例外としてあるかと思う。
大塲さん:冨永さんと同じで、新聞が出るまで外に出してはいけないというのが原則なのですが、例えば一人称で「」を付けて発言を引用したり、ある原稿に対して第三者の立場でコメントをもらったり、専門的なものだったりという場合には、その意図を間違えてはいけないのでご相談することもある。
でも、これはあくまで例外。もちろん確認してもらえるのであれば、確認してもらいたいのはやまやまだが、やっぱり原則があるので。
ただインタビュー記事については、一人称で語ってもらう場合であれば、基本的には新聞が出る直前まですべて取材した方に渡して、見出しも含めて最後まで議論するようにしている。
林さん:個人的には、取材を受けて話した以上は、ある意味あきらめている。話した内容が後で確認できなくても話したことは間違いないので、あえて確認しなくても私はいいというスタンスで、東日本大震災以降ずっと対応している。
ただ、確認を求めないのなら責任をもって間違ったことは書くなと。今回のダム湖の記事についても、間違ったことをいろいろ書かれたことが非常に問題だと思っている。

おわりに
今回はパネラーの方の話を中心に、研究者とメディアの視点からそれぞれの経験談や実情などを語っていただきました。
メディアを通して社会と“対話”するためには、どういった心構えが必要なのか?それぞれが持っている経験を共有することで、これからの参考にしていきたいと思います。
最後に、今回のワークショップを一緒に企画した対話オフィスメンバーで、サイエンスライターとしても活躍されている佐野和美さんから科学雑誌の場合の一般紙の取材との違いについてコメントがあり、そして国環研の立川理事、江守さんからワークショップ全体についてのまとめのコメントがありましたのでご紹介します。
佐野 和美
(帝京大学理工学部 講師/サイエンスライター/対話オフィスメンバー)
「サイエンスライターの場合は、基本的にニュースを紹介するというよりは研究成果を紹介するため、取材した研究者への確認は必ずしている。
また、私の場合はもともとのバックグラウンドがあるので、基礎研究の難しさや研究者側の事情も把握しているため、編集部と研究者の間に立った記事を作成するようにしている。
科学雑誌は、科学に興味ある人が読者層になるので、一般紙のようなセンセーショナルな見出しの記事を書かなくても読んでもらえるため、そういった意味では一般の取材などとは少し違うと思っている」

立川 裕隆(国立環境研究所 理事)
「研究所として社会ニーズに対応するという観点から、一般の方に参加いただくというのは非常に重要な点であり、報道に期待している部分はわれわれ自身にもある。
また、報道の側から見た場合、国環研の研究者は専門家として期待されているわけなので、そういったところで活躍していくのも本当に大切なことだと思う。
ただ、物事そんなに簡単に白黒つくわけでもなく、それをどう伝えていくのか難しい点がある。それから、守備範囲を外れそうなところはそれをはっきり言わないと、問題が生じやすい。
また、話したものがすべて掲載されるわけではないので、その中から切り取られるということを意識して、どこがポイントなのかわかりやすく伝えるということが大事だと思う。
なお、取材を受ける際には研究者としての責任感を持って発言することが大切であり、一方で、悪いことが起きた場合にはその責任と対策を取るというのが役所になるので、事前に広報室に共有してもらえると、スムーズな対応ができるので協力いただきたい」

江守 正多(対話オフィス代表)
「今回は、特にメディア側の視点を聞くことができ、どんな種類の記者がいて、どんな気持ちで書いているのか、どんな制約があるのかなどを理解することができた。そして、われわれもそれに対応するという能力をこれからつけていけたらと思った。
あとは取材に答える以上は、責任をもって、リスクを考えて、そして伝えたいことを伝えるという気持ちを持ってのぞむことが大切かと。
みなさんには、相手に伝えてやろうという意気込みを持って、かつ、楽しんでメディアと付き合ってもらえたらと思う」(終)
[掲載日:2018年3月30日]
取材、構成、文・前田 和(対話オフィス)
写真・成田正司(企画部広報室)
参考関連リンク
●対話オフィス「セシウムと将来リスク」
https://taiwa.nies.go.jp/colum/cesium.html
対話オフィスの関連記事
●2018年度ワークショップ「研究をうまく伝える秘訣とは?『ことば』のギャップを考える」
https://taiwa.nies.go.jp/activity/workshop2018.html