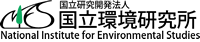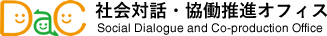シンポジウム「自動車タイヤ由来のマイクロプラスチックと添加剤について考える~現状理解と今後の課題~」を開催しました
はじめに
国立環境研究所 資源循環領域は、社会対話・協働推進オフィス(対話オフィス)と協働で、自動車タイヤ由来のマイクロプラスチックと添加剤について、専門家と参加者が一緒に考えるシンポジウムを都内会場とウェビナーのハイブリッド形式で開催しました。(※注)
現地会場には約70名、ウェビナーでは約400名の方にご参加いただきました。当日ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

現地会場の様子

登壇者のひとり、当研究所の鈴木剛室長
※シンポジウムのイベントページはこちら。事前&当日いただいた質問に登壇者が回答したQ&Aリストを追加掲載。
※本シンポジウムは、環境研究総合推進費「【1-2204】海洋流出マイクロプラスチックの物理・化学的特性に基づく汚染実態把握と生物影響評価」、「【5-2203】タイヤ摩耗粉塵を含む非排気由来の粒子排出実態に関する研究」の成果に関する公開イベントとして実施いたしました。
当日のプログラムと、意見交換の様子
本シンポジウムでは、環境行政や産業界の対応および専門家から、最新の情報、研究成果などの話題提供を行ったほか、後半では参加者からの質問をもとに意見交換する討論の時間を設けました。
当日は全体の司会を対話オフィスの渡邉陽子が務め、討論でのファシリテーターは当研究所の鈴木剛(資源循環領域 資源循環基盤技術研究室室長)が行いました。
【当日のプログラム】※敬称略、所属等は2025年3月当時
講演1.「プラスチック汚染に対する国内外の動向と環境省の取り組み」
環境省 水・大気環境局海洋環境課海洋プラスチック汚染対策室 長谷代子
講演2.「タイヤ業界の取組みについて」
一般社団法人 日本自動車タイヤ協会 環境部兼技術部 時田晴樹
講演3.「タイヤ摩耗粉塵を含む非排気由来の粒子排出実態について」
日本自動車研究所 環境研究部 伊藤晃佳
講演4.「海洋流出マイクロプラスチックの物理・化学的特性に基づく汚染実態把握と生物影響評価~自動車タイヤ粒子に着目して~」
国立環境研究所 資源循環領域 鈴木剛
愛媛大学 沿岸環境科学研究センター 仲山慶
鹿児島大学 水産学部 宇野誠一
愛媛大学 沿岸環境科学研究センター 国末達也
討論 設問2題について登壇者らが意見交換
設問1:流出インベントリの精緻化と対策への展開
設問2:持続可能な自動車タイヤの使用にむけた産官学民連永による協働体制構築のために
シンポジウムの参加登録時には、参加者のみなさんからの声を募る事前アンケートを実施しました。産官学民の様々なステークホルダーの方々から、ご質問やご意見をいただき、汚染実態や生物への影響などをはじめ様々な観点で関心が高いことが分かりました。

事前アンケートのまとめ
事前アンケートの内容をもとに最後の討論では、現時点で明確な解決策が見えていないものとして、2つの設問を設定しました。
設問1:流出インベントリの精緻化と対策への展開
設問2:持続可能な自動車タイヤの使用にむけた産官学民連携による協働体制構築のために
まず設問1では、マイクロプラスチックの中で最も多いと推計されている自動車タイヤ摩耗粉じんの環境/海洋流出について、効果的かつ効率的にタイヤ摩耗粉じんの流出を防ぐために、“いつ”、“どこから”、“どれくらい”、“どのように”流出しているのかを理解するために、それぞれの立場でできることや求めていることなどについて話しました。
■登壇者からのコメント
国環研・愛媛大学から・・・
・排出源が分かってきた中で、出てきているデータに濃度差がある。その意味するところをしっかりと明確にしていきたい。
・流出インベントリ(日本)の解像度を上げていきたい。
・環境中に出た後のより自然に近い実態調査のために、従来より適した材料(CMTT《タイヤ凍結粉砕試料》だけでなくTRWP《タイヤと道路の摩擦により発生する摩耗粉じん》のようなもの)を求めている。
・路面から出たものが集水桝などを通ったときに、どこで減っているのかなどを見ていきたい。
自動車研究所から・・・
・現状は、より正しいタイヤ摩耗粉じん排出量の算定を進めているところ。
・そのためには、タイヤの摩耗についての代表的/典型的なタイヤが何か、が明らかになると、非常に有用。ただし、その際の費用負担は問題。
タイヤ協会から・・・
・TRWPの環境や海洋への排出量は、様々な仮定のもと推計されたものが公表されている。
・科学的アプローチでの調査が大切。
環境省から・・・
・水、大気、土壌など環境全体を見る視点で考え把握していきたい。
・化学物質をみるのであれば別のインベントリが必要では。
・共通のガイドラインを通して他国と議論できるよう共通化していきたい。

意見交換の様子
次に設問2では、発生と流出の実態把握、随伴する添加剤や非意図的生成物の種類や量、生物・生態系への影響、ガソリン車と電気自動車での違いの理解などに、産官学民が協働して取り組んでいくためには、どのような仕組みがあればよいと思うかについて話しました。
■登壇者からのコメント
国環研・愛媛大学から・・・
・求める情報が公になっていない場合に、メーカーや環境省から情報がオープンにもらえる関係があればいいと思う。
・対話型のシンポジウムで意見交換し、データを共有し合う、その結果も共有したい。
・大学の立場として対応できる人材育成を進めていく。
自動車研究所から・・・
・連携して何をやるかも重要だが、どのように連携/会話するかも重要。
・色々な立場の人が話し合うことができる場で悩みを共有しあうような、継続した場の開催を期待したい。
タイヤ協会から・・・
・欧州では産官学民からなる「TRWP Platform」が2018年に立ち上がり、緩和策等の検討がなされた。この先行事例が参考になるのでは。
環境省から・・・
・産学官の対話をめざしプラスチック・スマートの懇話会を設置した。コロナ禍のスタートだったが、直接話ができる場の必要性を実感している。
おわりに
開催後のアンケートでは、ほとんどの参加者から「新たな発見があった」との回答をいただき、「最新の状況を理解することができました」「タイヤ由来の粉じんについての概要と考えられる影響が分かりやすかった。」「車が必須な地域にいますので、タイヤだけではなく、道路の粉じんも関係することが分かり興味深かったです」「産官学の各取り組み、各視点での考え方を知ることができた」「今後もこのような対話型のシンポジウムがあるとよいと思いました。」といった感想が得られました。
今回いただいたご意見は、今後の課題解決、研究活動などに活かしていきたいと思います。 (終)
[掲載日:2025年4月10日]
構成、文・渡邉 陽子(対話オフィス)
写真・成田正司(企画部広報室)
参考関連リンク
●環境省「(概要)環境中流出プラスチックに関する重点課題(生物・生態系影響と実態)」(外部リンク/PDF)
https://www.env.go.jp/content/000255574.pdf
●環境省「日本の海洋プラスチックごみ流出量の推計」(外部リンク)
https://www.env.go.jp/water/marine_litter/survey/estimates_plastic_waste_in_Japan.html
●環境省「マイクロプラスチックの生物生態系影響(水生生物)」(外部リンク)
https://www.env.go.jp/water/marine_litter/survey/ecological_impact.html
●環境省「PRTR制度運用・データ活用事業」(外部リンク/PDF)
https://www.env.go.jp/guide/budget/spv_eff/review_h29/attach/siryo2.pdf
●環境省「令和5年度PRTRデータの概要等について-化学物質の排出量・移動量の集計結果等-」(外部リンク)
https://www.env.go.jp/press/press_04462.html
●環境省「マイクロプラスチック削減に向けたグッド・プラクティス集」(外部リンク)
https://www.env.go.jp/water/post_113_00005.html
●環境省「一般向けマイクロプラチック発生抑制・流出抑制対策リーフレット」(外部リンク)
https://www.env.go.jp/page_00357.html
●対話オフィス「シンポジウムのお知らせ:自動車タイヤ由来のマイクロプラスチックと添加剤について考える~現状理解と今後の課題~」
https://taiwa.nies.go.jp/activity/symposium2025_0307.html
※事前&当日いただいた質問に登壇者が回答したQ&Aリストを追加掲載。