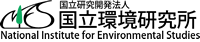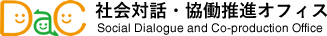※回答内容や回答者の所属等は、掲載当時のものです。
国立環境研究所ではストロンチウム90の調査を行っていますか?
Q.福島第一原発事故により環境中に放出された放射性物質のうち、セシウムだけでなくストロンチウム90も人体への危険が大きいと聞きます。国立環境研究所ではストロンチウム90の調査を行っていないのでしょうか?
回答:福島支部 環境影響評価研究室 林室長(2018年2月26日)
A. ストロンチウム90の広域モニタリング調査は、環境省(※注1)、文科省(※注2)が実施し、ストロンチウム90による環境汚染のおおよその実態は把握されており、放射性セシウムに比べその存在量は非常に少ないことが判明しています。
一方で、我々の災害環境研究プログラム(※注3)では、主に避難指示解除区域を対象に、地域住民の生活環境おいて、どの程度のリスクがあるのか(リスク評価)、そのリスクを避けるためにはどうすればいいのか(リスク管理)に役立つデータの取得を目的としています。
その観点からは、対象区域におけるストロンチウム90は、影響は極めて小さいと考えられます。
また、そもそもストロンチウム90の存在量が少ないため、飛散したストロンチウム90がどこに移動しているのかを把握(挙動評価)するための測定には、多大な時間とコストが必要です(※注4)。
これらのことを踏まえ、暮らしや健康への影響が、ストロンチウム90よりも、明らかに大きい放射性セシウムの測定・調査に、研究スタッフや財源などを優先的に割り当てることが望ましいと判断しています。
ただ、広く環境中に存在するストロンチウム90の移動と再集積、生物への移行を明らかにすることが当研究所含め研究機関の役割であることは理解しています。
そのため、ストロンチウム90についてより効果的に分析する体制づくりは重要であると考えています。
これまでにも迅速な分析手法の開発と、水、土壌、生物試料での分析への適用を実施(※注5)しました。現在も測定方法の簡易化の研究等は継続(※注6)しています。
※注1 環境省調査はこちら(外部リンク)
上記ページの最後に、「水生生物」のカテゴリーがあります。1~3か月ごとにわかれている調査結果の中からご希望の期間をクリックしていただき、「調査概要及び結果」欄にある「調査結果一覧」のPDFをご参考ください。PDFの資料では、水域と底質それぞれについて、データ表の一番右端の列にストロンチウム90の測定結果が記載されています。一例として、平成28年度12月調査結果(外部リンク/PDF)を添付しましたのでご確認ください。放射性セシウムに比べて非常に濃度が低いことが判断できます。
※注2 文科省調査はこちら(外部リンク/PDF)
上記ページの3枚目にある次の記述をご覧ください。「セシウム134、137の50年間積算実効線量に比べて、プルトニウムや放射性ストロンチウムの50年間積算実効線量は非常に小さいことから、今後の被ばく線量評価や除染対策においては、セシウム134、137の沈着量に着目していくことが適切であると考える」
※注3 災害環境研究プログラムについてはこちら(外部リンク/PDF)
上記ページ内「災害研究プログラム」の「PG1:環境回復研究」で、放射性物質により汚染された地域の環境回復を目的にしています。
※注4 ストロンチウム90の測定には、現在、公定法(文部科学省法)と迅速法(固相抽出ディスク法)の2通りが用いられています。放射性ストロンチウムはβ線のみ放出するのでそのβ線を測定するのですが、γ線と違って固有のエネルギーを持たないため、試料からまずストロンチウムのみを抽出する前処理が必要となります。前処理については、公定法では20段階以上の化学処理を要します。さらに、より精度良く測定するためイットリウム90へ壊変させるために、前処理後測定まで2週間は静置しておく必要があり、全体として測定までに2から3週間の時間を要します。
※注5 国立環境研究所「災害環境研究成果報告書」より。詳細はこちら(外部リンク/PDF※230ページ参照)
※注6 国立環境研究所「PG1(放射能汚染廃棄物) 環境回復研究プログラム」より。詳細はこちら(外部リンク)